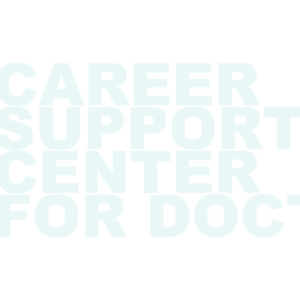リアル薬屋のひとりごと(川西良典)
 薬屋のひとりごとをご覧になっただろうか。
薬屋のひとりごとをご覧になっただろうか。
よみがえりの薬が用いられる場面があり、その作用はまるで全身麻酔のようである。曼荼羅華を使っているのではないかと考察されていたが、曼荼羅華は朝鮮アサガオであり臨床麻酔学会の象徴として知られている。
ただ患者は麻酔科医の管理を受けないため、相応の後遺症が避けられない。
麻酔科医は死んだように眠らせるのみならず、さらに手術侵襲からさえ患者を守りながら後遺症なくよみがえらせることを生業とする。これを生業とするのに一朝一夕でというわけにはいかないが、それでも麻酔科医は駆け出し始めたその日から、いきなり全身麻酔をかけることができる。もちろんインストラクターと二人羽織だ。麻酔科医には針職人としての職務も存在する。
しかし手技における失敗を繰り返すことは、近年許されがたくなっている。そのため挿管はもとより点滴・動脈ラインとも十分にモデルを用いた指導を行い、臨床でのフィードバックを行っている。加えて国立循環器病研究センター帰りの医師たちによる、エコーガイド下穿刺の指導も浸透しており、日々そこここで駆け出し針職人たちの神業が展開されている。
3か月もすると麻酔の外勤が始まる。アウェイでの麻酔は緊張の連続だが、一気に臨床能力が向上する。そのころから一般的な全身麻酔に加え、小児・呼吸器・脳外科、時には心臓の麻酔と専門医試験に対応した症例にも遭遇するようになるが、基本の全身麻酔力も同時に涵養される。
 少なくとも1年は指導医とともに麻酔を行い、安全に臨床能力を向上してもらう。学会発表の指導も行い生涯学習の基礎も固めてもらう。2年目にもなると自分で麻酔をしたくてうずうずしてくる。いつでも相談に乗れる環境は維持しながらも、陰ながら臨床能力の向上を期待する毎日が始まる。過干渉を避け自己研鑽を期待する指導スタイルが徳大スタイルだと思っている。
少なくとも1年は指導医とともに麻酔を行い、安全に臨床能力を向上してもらう。学会発表の指導も行い生涯学習の基礎も固めてもらう。2年目にもなると自分で麻酔をしたくてうずうずしてくる。いつでも相談に乗れる環境は維持しながらも、陰ながら臨床能力の向上を期待する毎日が始まる。過干渉を避け自己研鑽を期待する指導スタイルが徳大スタイルだと思っている。
徳島大学病院 麻酔科 川西 良典